※このページではフリーランス国際協力師原貫太の本『世界を無視しない大人になるために 僕がアフリカで見た「本当の」国際協力』を第一章まで公開しています。

クリックすると購入ページへと飛びます。

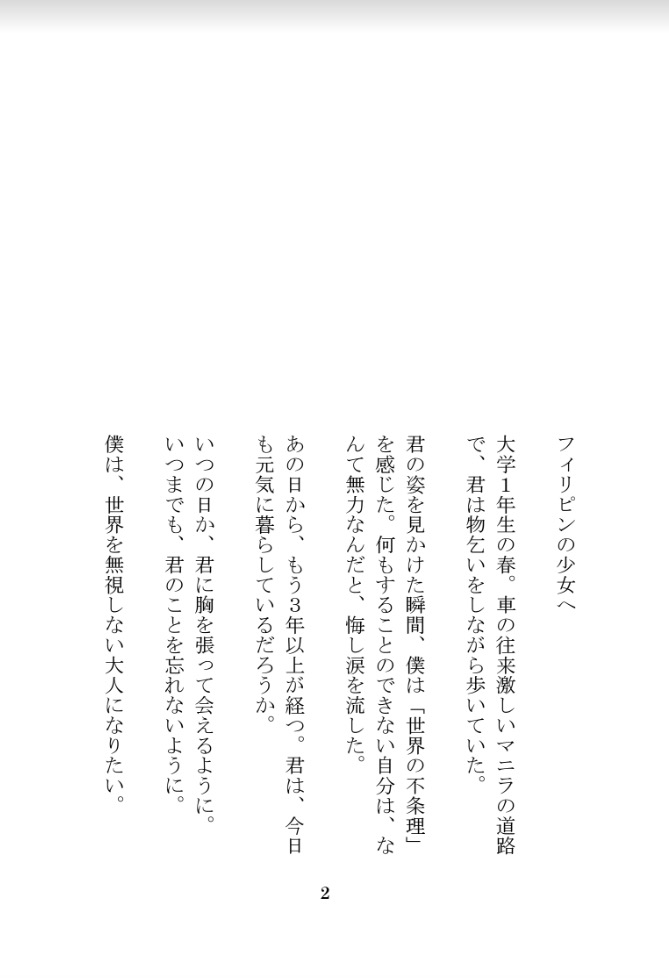
はじめに
この本では、僕が認定NPO法人テラ・ルネッサンスのインターン生として携わったアフリカでの活動、主にはウガンダ北部における元子ども兵社会復帰支援プロジェクト、またウガンダ最北部の南スーダン難民居住区で行った調査活動について、この活動に携わるようになった経緯や、僕個人が活動を通じて感じたことなどとあわせて書いている。
多くの人にとって、特に僕と同じ大学生のような若い世代の人にとっては、アフリカは遠くの世界であり、子ども兵や難民の問題は「どこか遠くの世界の出来事」に感じてしまうかもしれない。僕も、その一人だった。
伝えることは、時に葛藤を生む。どのようにすれば、自分が現地で見た・聞いた・感じた「不条理」を、受け手の心の奥底にまで届けることができるのか。いくら伝えたとしても、その先の行動までもたらすことができなければ結局は無意味ではないだろうか。そもそも、僕のような小さな人間に「世界の不条理」を伝える権利があるのか―。
日本、それも早稲田大学に通えるほど恵まれた環境で育ってきた僕は、子ども兵、難民、ストリートチルドレンなど、途上国で日々「不条理」に晒される人々と接するたびに、もはや変えることなど到底できないような「格差」を痛感する。
お洒落なカフェで友人たちと会話を楽しみながら、自分の好きな分だけ食べる日本の大学生がいる一方で、なぜその日食べるものを得るために、学校にも通わず、朝から晩まで駅で荷物運びの仕事に汗を流すバングラデシュの少年がいるのか。
水泳とピアノを習いながら塾にも通い、クリスマスには親からゲームを買ってもらう日本の小学生がいる一方で、なぜ銃を持たされ戦場で人殺しに従事させられるウガンダの少年兵がいるのか。
もちろん、その「格差」は単純に先進国と途上国との間にあるだけのものではなく、先進国内、途上国内にも存在するものではあるが、いずれにせよ日本の中でも恵まれた環境に身を置いている僕は、そこと途上国で目の当たりにした現状との間に、絶望的なまでに大きな「格差」を痛感してしまう。
今改めて思う。僕にとって「伝える」という行為は、「世界の不条理」に抗うための、必要最低限の行為なのだと。
「苦しみはそれを見た者に義務を負わせる」という言葉もあるように、現場に足を運んだ人間にとって、その現状を「伝える」ことは、このどうしようもないほど広がってしまった「格差」を是正するための、必要最低限の行為なのだと。
そしてまた、Solution-Oriented(ソリューション・オリエンティド)、つまり「問題を根本的に解決する」という志向を持って活動するテラ・ルネッサンスでインターンの経験を積んだことによって、世界の諸問題を根本的に解決していくためには、いわゆる途上国の「現場」における活動のみならず、先進国に暮らす僕たちの意識や行動を変えていかなくてはならないのだと、改めて考えるように至った。
フィリピンで物乞いをする少女を目の当たりにし、悔しくて、悔しくて涙が出た時から、もう3年が経つ。何も特別な活動をしているとは思っていない。これからの社会を担う僕たちが、未来に生まれてくる子どもたちに、安心して自分たちの世界を見せられるように。
この本を読んだ一人でも多くの人が、社会/世界の問題に主体者としての意識を持ち、新しい一歩を踏み出すことを願って止まない。

バングラデシュで出会った、ポリオを患っているにも関わらず路上に寝かせられ、物乞いする少年。僕はこの光景を、今でも時々思い出す。
〈目次〉
はじめに
プロローグ 手が震えた
第一章 アイーシャさんとの出会い
第二章 約束を守れるか
第三章 3万人の子ども兵たち
第四章 本当に意味のある支援
第五章 立ち上がる元子ども兵たち
第六章 忘れてはいけないこと 南スーダン難民との出会い
エピローグ 世界を無視しない大人になるために
プロローグ 手が震えた

元少女兵アイーシャさん(仮名)へのインタビューの様子
メモを取る手が、震えた
2016年1月、東アフリカに位置するウガンダ共和国、北部最大の都市グル。大学2年時に学生国際協力団体(学生NGO)を立ち上げて、それまでにもストリートチルドレンやスラム(貧困地区)に暮らす人々などから何度も話を聞いてきた僕は、「冷静に、落ち着いて、インタビューしよう」と心に決めていた。
しかし、「元少女兵」を前にして僕は、メモを取る手が震えてしまった。
「『どこか遠くの世界の出来事』に過ぎなかった子ども兵の問題が、今、僕の目の前にある」。そのリアルに、理解が追い付かなかった。元少女兵が語るひとつ一つの言葉を聞き、彼女にどのような声をかけてあげればいいのか、分からなかった。
「大変だったね」「これからの社会復帰に向けて頑張ろう」。そんな安っぽい言葉ですら、僕の口から出てくることは無かった。
子ども兵問題を初めて知ったのは、いつだっただろう。たしか、僕がまだ高校生だった頃だ。何かの本で知り、強い衝撃を受けたのを何となく記憶している。「世界にはひどい人たちがいるものだ」「こんなの、嘘でしょ…」。その実態があまりにも不条理すぎるからか、子ども兵という問題に対して当時の僕は、「どこか遠くの世界の出来事」と割り切っていたかもしれない。
その頃は、まだ「他者」という概念について、深く考えることなどなかった。僕が生きるこの地球上で、僕と同じようなヒトが、今この瞬間も「不条理」に晒されている。そんなことは気に留めていなくても、日本で幸せに生きていける。
きっとこの本を読んでいるあなたも、子ども兵問題は「どこか遠くの世界の出来事」と感じているかもしれない。僕も、そうだった。
そもそも子ども兵という「労働」は、「最悪の形態の児童労働条約」(1999年)によって、売春や債務奴隷と並び「最悪の形態の児童労働」と定義されている。僕は大学2年時に立ち上げた団体のスタッフとして、約2年間児童労働問題(ストリートチルドレン問題)に取り組んできたが、その過程で「最悪の形態の児童労働としての子ども兵」に問題意識を深めていった。
一方で、大学3年時の秋からは交換留学生として渡米。国際関係論を専攻し、紛争や暴力について考える日々を送った。その過程でまた、紛争下で生きる「子ども」という存在に問題意識を持った。アメリカ留学中も、様々な資料を通して子ども兵問題に対する理解を深めていった。
想像力と感受性が人一倍強い僕は、世界中で起こるあらゆる出来事に対し、そこに自分との繋がりを求め、時に悲しさを感じ、時に悔しさを感じ、時に喜びを感じる。しかし、子ども兵問題はあまりに不条理すぎるからか、それは僕にとって「どこか遠くの世界の出来事」であり続けた。初めてこの問題を知った高校生の時から、進歩していない。
僕は、それが悔しかった。問題意識が朧げなものから明確なものへとなればなるほど、その問題を「どこか遠くの世界の出来事」として終わらせたくなかった。だから僕は、一人でアフリカへ行くことを決めた。
アフリカへの渡航を決めた時は、2015年11月中旬。当時の僕はアメリカに留学していた。学期末の試験やレポートに向けて忙しくなっていく時期、大学の勉強と並行して、アフリカ渡航に向けた準備を進めた。
アフリカに行ったことはそれまでに一度も無い。コネクションもほぼゼロの状態からスタートした。
「アフリカで子ども兵問題を調査したい」。アメリカ留学の出発前日に観たNHKスペシャルで、テラ・ルネッサンスの元子ども兵社会復帰支援が特集されていたのを思い出した僕は、早速連絡を取り、訪問の許諾をもらった。
そして2015年12月31日にニューヨークを発ち、機内で新年を迎えた僕は、アフリカへと向かった。

紙版の購入はこちら
Kindle版の購入はこちら
第一章 アイーシャさんとの出会い

アイーシャさん(写真右)
人生で初めて出会った元子ども兵
「拘束された時から、密林を歩き回る生活が始まりました」。そう話を切り出した彼女が、僕が人生で初めて出会った元子ども兵だった。
ウガンダ首都カンパラから、地元の人が使うバスに乗って約7時間。テラ・ルネッサンスのウガンダ事務所は、北部最大の都市グルにある。首都カンパラを始めとする南部と比べると、20年以上続いた紛争の影響によって、北部では未だ多くの人々が貧困下での生活を強いられており、気温も高く乾燥しているため、決して生活しやすい環境とは言えない。
外国人もまばらにしか見られないグル、そこに僕は一人で足を運び、8期目の元子ども兵としてテラ・ルネッサンスの支援を受けている元少女兵アイーシャさん(仮名)から話を聞くことができた。
以下は、アイーシャさんと通訳をしてくれた現地スタッフリチャードの発言に基づいている。ウガンダ人の多くが英語を話すことができる一方で、子ども時代に誘拐され教育機会を失った元子ども兵の多くは、英語をほとんど話すことができない。そのため、通訳を介し、英語と現地の言葉アチョリ語を混ぜながらインタビューを行った。
2000年12月19日の真夜中、アイーシャさん(仮名)は反政府軍である神の抵抗軍(LRA)に誘拐された。当時わずか12歳だった。そこには、数え切れないほど多くの困難が彼女を待ち受けていた。
「一日中重い荷物を持たされ、森の中を走りました。休息は夜に少し取るだけ。非常に辛く、苦しいものでした」「水も食料もない状態で、本当に辛かったです。軍隊にいる間、常に戦闘が続いていました。昔はいつ死んでもおかしくないという思いで生きていました」。
「神の抵抗軍」での厳しい生活に慣れることは、非常に難しかったと彼女は話す。人が殺されるところを、数え切れないほど目の当たりにした。人を殺傷することや、軍隊という過酷な環境に彼女を「慣れ」させるため、「神の抵抗軍」はアイーシャさんに人殺しの現場を見せたがっていたのだ。
2000年から2003年までの3年間、北部ウガンダの茂みを歩き回った。その後、ウガンダ政府軍による「神の抵抗軍」の掃討が勢いを増すと、ウガンダに滞在することは厳しくなる。2004年、彼女らは合計4回にわたって拠点をスーダン内へと移した。
「(スーダンでは)とても長い距離を歩かされて、4日間ずっと移動し続けたこともありました」。
スーダンに拠点を置いている間も、越境してきたウガンダ政府軍によって何度か掃討があったため、拠点を更にコンゴ民主共和国へと移した。彼女は、日夜「神の抵抗軍」と行動を共にしなければならなかった。それは、若い彼女にとって非常に辛く、苦しみを伴うものだった。

ウガンダ北部で撮影した夕焼け
コンゴ民主共和国滞在時、彼女は脱走を試みる。脱走のリスクは当然大きかった。脱走に失敗して再度捕まれば、それに対する上官からの罰は非常に厳しく、非人道さを極めていた。
他の子ども兵が脱走することを防ぐために、脱走しようとして捕まった者は、見せしめとしてひどい罰を受けるのだ。時にそれは、命を失う事にも繋がった。「ある夜に他の仲間と脱走を試みましたが、捕まり、鞭で200回叩かれました。それからは脱走する事は諦めました」。
コンゴの密林を、反乱軍と共に動き回る。そんな生活が長く続いたある日、彼女に子どもが産まれる。少女兵の多くは、従軍中に反政府軍の兵士と強制結婚をさせられ、子どもを授かることもある。中には、兵士との性交渉中にHIVに感染し、帰還後もエイズを発症する、また穢れた存在だと差別や偏見を受け、コミュニティから疎外されるなど、社会復帰がより困難な状態に置かれる。
「幼い子どもを連れながら、政府軍から逃れるために茂みの中を走るのはとても大変でした」。子どもを抱き、銃を担ぎ、身の回りの物を背負い、茂みの中を走る。その辛さを言葉にすることはできないと、彼女は語る。
コンゴから中央アフリカ共和国に移動し、またコンゴに戻り…、そんな生活が長く続いた。2014年、彼女は政府軍に救出されたが、2000年からの実に14年間、彼女は「少女兵」としての生活を強いられた。
救出後の生活は、茂みでの生活とは全く違うと彼女は語る。「人々はお互いの権利を尊重し合っています」。
拘束されていた頃は何も言う事ができず、ただ上官からの命令に従うしかなかった。荷物を運べと言われれば荷物を運び、村を襲えと言われれば村を襲った。命令に背けば、時には殺されるまで罰が下された。
「拘束から逃れて戻ってきた時、私には3人の子どもがいました。持ち物は何もありませんでした。それでも、幸せでした。拘束から逃れられた、ただそれだけで幸せに感じました」。
テラ・ルネッサンスで訓練を受けている心境を、彼女はこう語る。
「テラ・ルネッサンスの訓練所では、多くの技術を身につけることができています。以前はずっと人に頼り、物を借りていましたが、今の自分は能力を身につけ、自分で物事を行うことができるようになってきました」
「テラ・ルネッサンスで技術訓練や基礎教育を受けられる、その事が、今の自分を幸せにしてくれます。ここでの学びを活かし、卒業後はもう一度、自分の人生を変えたい。そして、子どもたちの未来を支えたい。そう願っています」。

テラ・ルネッサンスの施設でミシンの訓練を受けるアイ―シャさんたち
紙版の購入はこちら
Kindle版の購入はこちら
眠れない夜
アフリカに行く前にも、ストリートチルドレンやスラム(貧困地区)に暮らす人々へのインタビューを経験していた僕は、元子ども兵から話を聞くことに対しても、「できる限り、いつものように振舞おう」と思っていた。テラ・ルネッサンスの施設にやって来る前にも、隣国ルワンダでの虐殺の跡地巡りや、ウガンダ首都カンパラでのHIV/エイズ孤児へのインタビューを行っていたため、その気持ちは一層持っていた。
しかし、アイーシャさんへのインタビューが終わった後、僕は彼女に何と言葉をかけてあげるべきなのか、分からなかった。
彼女が自身の経験について語っている時の表情を端的に表すと、辛そうで、悲しそうなのだ。これまでのインタビュー、例えばバングラデシュで行ったストリートチルドレンへのインタビューでは、「親から暴力を受けたから家出した」「日中は仕事をしないと生きていけないから学校には通えない」など、辛い状況を語りながらも、彼らが時々見せる笑顔が印象的だった。
もちろん、冷静に彼らの「笑顔の裏」を想像する事が大切であり、それを知るための努力もしなければならないが、必死に毎日を生き抜いている彼らの強さもまた、僕には印象的だった。
しかしアイーシャさんは、もう本当に、辛そうで、悲しそうなのだ。社会的に弱い立場に置かれた人から直接話を聞く時、僕は「同情」ではなく、「共感」できるようにと心がけてきた。「可哀想だな」と同情し、外から彼らのことをみてしまうのではなく、できる限り彼らと寄り添って、同じ目線から彼らの苦しみや痛みに想いを馳せる。
しかし、アイーシャさんへのインタビューでは、「共感」など考える余裕が全くなかった。彼女が話す過酷な情景を想像することはできても、まるで映画を視聴しているかのように、「外」からその光景を頭の中に思い描いているに過ぎない。
インタビューが終わった後、僕は彼女に向かってただ一言、「話してくれてありがとう」と声をかけることしかできなかった。
その晩、僕はなかなか眠りにつくことができなかった。トイレも風呂も付いていない一泊1000円の安宿。ベッドに寝転がり、蚊帳の中に入って一人天井を眺めていた。「彼女が子ども兵として過ごしていた期間、僕は日本で何をしていただろう」「彼女はいったいどんな思いで今日のインタビューに臨んでくれたのだろう」「なぜこの世界はこれほどまでに不条理なのだろう」。
大好きなMr. Childrenの歌『タガタメ』を聴きながら、涙が出た。
テラ・ルネッサンスの日本人スタッフから後で聞いて分かったことだが、一人でふらっとやってきた日本の大学生に対して、ウガンダの現地スタッフが元子ども兵へのインタビュー、それも従軍中の話についてのインタビューを許可するというのは、かなり珍しいことだったようだ。プロのジャーナリストであっても、元子ども兵の心理状態を考慮して、取材を拒否することもあるらしい。
テラ・ルネッサンスのウガンダ事務所を離れる時、現地スタッフに対して自然と出た言葉がある。「I will be back」(戻ってきます)。
「苦しみはそれを見た者に義務を負わせる」。アイーシャさんの話を聞いた者として、彼女の苦しみを見た者として、「何か」をしなければならない。そう決心し、僕はアフリカを離れ、留学中のアメリカへと戻った。

ウガンダ北部に暮らす女の子
続きは本編をご覧ください。
紙版の購入はこちら
Kindle版の購入はこちら